会社員としての収入が少ないと思って副業を開始する人は、この令和時代になって増えてきたと思います。
様々な副業の中でも、とりわけ初期費用が少なく、空き時間を活用して行うことが出来る【ブログ】を行っている人も多いのではないでしょうか?
しかし、ブロガー界隈では「魔の3ヶ月」という格言(?)があります。
ブログ活動を続けるにあたって、活動自体を習慣にするのに3ヶ月はかかる、という意図での言葉ですが、その真の意味は、「ブログのネタが尽きて3ヶ月も続けられない」という現象です。
僕自身もこちらとは別のブログでネタが切れて続けられなくなりましたが、こちらのブログでは1年間継続しています。
そこには特別な裏技があるわけではなく、「ブログの本質」を考えると、継続するコツはたったの2つだけに絞ることが出来るということに気が付きました。
この2つを意識するだけで、ネタも切れず、記事の質もレベルアップも期待できます。是非、本記事で学んでいってください。
※今回参考にした書籍はこちら↓
【ブログの本質】とは?
まず、そもそも論で、「ブログとは何なのか?」について考えてみましょう。Googleで【ブログとは】と検索すると、まさかの一番上に総務省がブログの仕組みに関して解説している記事がありました。
その記事にはこのように記載されています。
ブログは、自分の考えや社会的な出来事に対する意見、物事に対する論評、他のWebサイトに対する情報などを公開するためのWebサイトのことです。
~中略~
最近では企業でも情報を公開したり、新しい商品やサービスの情報を公開したりする場合に利用されることが増えてきました。
ブログの仕組み|国民のための情報セキュリティサイト(総務省)
これまで、「ブログ」と聞くと、【Amebaブログ】などで芸能人が日記感覚で発信していることのイメージが強かったでしょう。
しかし、昨今では引用にもあるように、企業もブログのシステムを利用して情報発信をしています。企業が情報発信をする目的は、自社商品・サービスの販促のために、サイト閲覧者にその情報を伝えるためのツールとなってきています。
このような事象から、現代における【ブログの本質】とは、【価値を提供できる情報発信】であることが伺えます。
ネタ切れ解消法は2つ
この【ブログの本質】が【価値を提供できる情報発信】ということですが、人がネット検索をするにあたって、何に価値を感じるかというと、「自分が検索した疑問を解決してくれるサイト・記事」なんだと思います。
その本質に基づいてブログの記事を書くためのネタ作りのコツは以下の2つに集約されます。
- SNS上で何かに悩んでいる・困っている発信をしている人のために記事を書く。
- 自分の身近な人が疑問に思っていることに応える記事を書く。
それぞれ、少し掘り下げて解説していきます。その上で、実際にその方針で作成した記事も紹介するので、記事作成の参考にしてもらえたらと思います。
SNSで何かに悩んでいる・困っている発信をしている人のために記事を書く。

現代に生きる我々にはSNSを通じて、住んでいる場所も、名前も、顔すらも知らない人たちと繋がることが出来ます。
インターネットの世界はとても広いですから、中には、
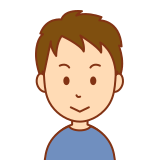
これってどう思いますか?
とか、
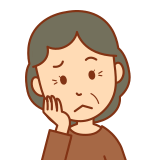
こんなことになっちゃった!どうしよう…。
など、疑問をつぶやいたり、その人自身の困った体験をつぶやいているツイートも時々目にします。
そういったツイートに対する答えや自分の知識でそのアカウントの疑問などを解決させてあげられるような記事を作っていきます。
実例①:投資家界隈で流行った【レバナス】
11月に楽天証券が【楽天レバレッジNASDAQ-100(通称:楽天レバナス)】という投資信託をリリースしてから、個人投資家界隈では購入報告や売買実績報告のツイートが増えました。
そのような状況の中、投資家アカウントは【レバナス肯定派】と【レバナス否定派】に2分されることになりました。
お互いをなじりあう過激派もいましたが、レバナスの評価額がどんどん下落していく中で、こんなツイートを目にしました。

長期で見たらNASDAQ-100は右肩上がりなんだから、ドルコスト平均法で積み立てていけば大丈夫だよね!
このツイートをみて、個人的には以下のように感じました。
ホントは不安に思ってるけど、その不安を払拭したくて、自分に言い聞かせてるようなツイートだなぁ…。
レバレッジファンドは普通のインデックスファンドと違う特性をもっているけど、そういうものでもドルコスト平均法ってホントに有効なのかな?
という自分にも疑問が生まれたので、【本当にレバナスはドルコスト平均法で正解なのか?】というテーマで記事を作成しました。それがこちらです。
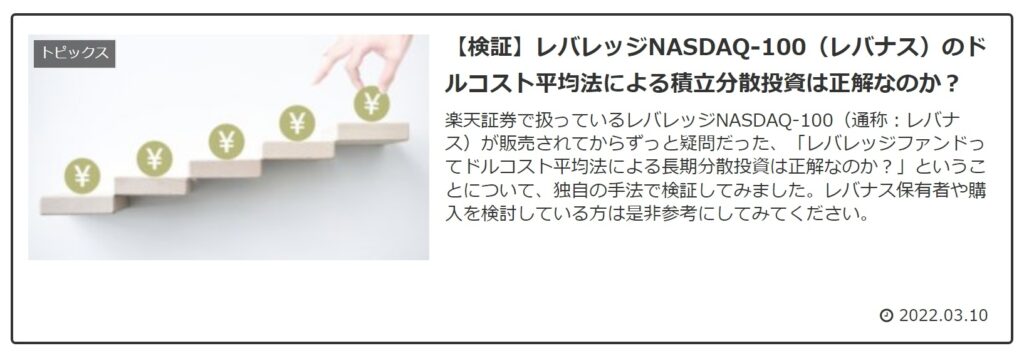
記事内には、実際に行った分析方法や、もちろん、結果・結論も明確にしています。この記事を作成して、どの程度レバナス投資家の人に影響があったのかまでは分かりませんが、1人でも認識をアップデートした方がいたら嬉しいですね。
実例②:世間的なトレンドだった【ゆうちょ銀行硬貨預け入れ有料化】
2022年1月から、ゆうちょ銀行が「硬貨預け入れには手数料を必要となる」ことをリリースして、テレビのワイドショーでも取り上げられるほどの世間的なトレンドになりました。
そんな中、このようなツイートを目にしました。

このようなことって、氷山の一角というか、1人がミスや失敗をしているということは、声を上げないだけで、他の人も失敗する可能性が潜んでいるものだったりします。
そこで、僕はこんなリツイートをしました。

このリツイートをきっかけに、こんな記事を作成しました。

ネット銀行から、メガバンク・地銀に至るまで、全国すべての銀行のホームページを閲覧して作成しました。
手間はメチャクチャかかりましたが、以外にも、こういった【○○一覧】系の記事は検索流入に掛かりやすいので、PVを稼ぎたい人はやり方の一つかもしれません。
自分の身近な人が疑問に思っていることに応える記事を書く

自分の身近な人との会話を基にすることも有用です。職場の同僚、学校や地元の友達、家族、恋人…。色んな人があなたの周りにはいますよね。
例えば、一緒にテレビを見ていたり、ネットサーフィンをしているなどの時に、こんなことをお互いで話したりしませんか?
○○ってどういうことなんだろうね?
そろそろこんな時期かぁ。どうしたら良いんだろうね?
この疑問を解決してあげられるような記事を作成してみましょう。
実例③:父の日プレゼント問題
5月の【母の日】と対を成す6月の【父の日】を控え、我が家では妻からこんな疑問を投げかけられました。
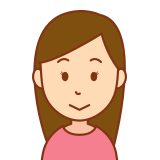
父の日って何プレゼントしたら良いか分かんなくない?
この疑問を耳にした時に、「確かになぁ…」と思いました。母の日はカーネーションやフラワーアレンジメントなどが定番ですが、「父の日の定番って無いよな」と思いませんか?
男目線になると、別に花を贈られても嬉しさはそこまでないし、過去にはネクタイやタイピン、ハンカチなどが定番だったでしょうが、クールビズなどが当たり前になった現代においてはネクタイ系は使いどころが減っているでしょう。
そんな疑問に応える形で、こんな記事を作成しました。
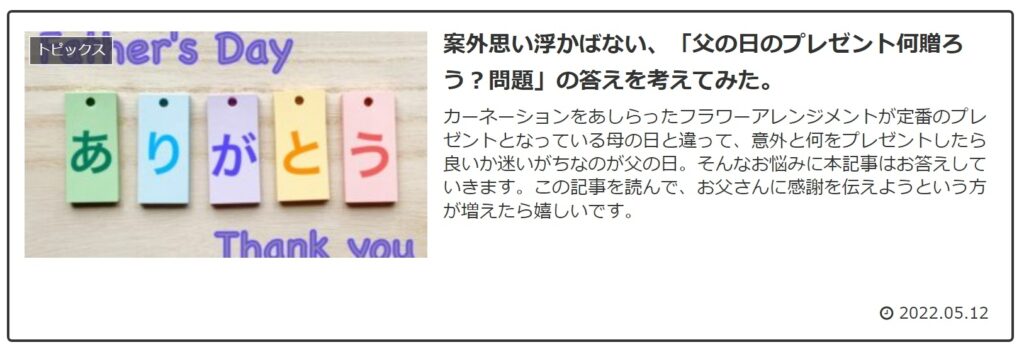
【おすすめ商品】ととすると、競合も多く、その多くは楽天などの通販サイトなどが発信している内容だったりするので、少しだけニッチな方向に路線を調整しています。
ブログ活動に重要なペルソナ設定には人との関わり合いを大切にしたい
ブログやマーケティングに関わる書籍や、ブロガー指南系YouTuberが口をそろえていることですが、ブログ運営にはペルソナ設定が大事だということです。
「ペルソナ(persona)」とは、サービス・商品の典型的なユーザー像のことで、マーケティングにおいて活用される概念です。
実際にその人物が実在しているかのように、年齢、性別、居住地、職業、役職、年収、趣味、特技、価値観、家族構成、生い立ち、休日の過ごし方、ライフスタイル……などリアリティのある詳細な情報を設定していきます。
ferret|今さら聞けない「ペルソナ」とは。意味やマーケティングでの活用方法、作り方も解説!
似た言葉で「ターゲット」という表現もありますが、ペルソナとは似て非なるものです。詳しいことはさておき、ざっくりこういう違いです。
- ターゲット→「こんな人達」という【層】を指す。
- ペルソナ→「この人」という【個人】を指す。
ターゲットは「浅く広く」を意識して考えますが、ペルソナは「深く狭く」を意識して考えます。
とは言っても、マーケティング業務をしたことない人・学んだことが無い人にとっては難しいですよね。実際、僕も難しかったです。
何が難しいというと、【架空の人物を作り上げる】ことなんですよね。
架空だから難しいので、【実在している人】を自分なりに細かくペルソナ分析して、「その人のためだけの記事を書こう!」くらいの気持ちの方がやりやすいです。
Twitterアカウントの向こう側には実在している人がいるし、身近な家族や友人などは正しく実在しているわけですから、その人たちをペルソナとして設定して記事を書いてみると良いでしょう。
まとめ
如何だったでしょうか?本記事の概要を以下にまとめます。
- ブログの本質は【価値ある情報発信】すること。
- 検索する人が何に価値を感じるかというと、「検索したこと(=検索者が疑問に思ったこと)を解決してくれるサイト・記事」であるということ。
- 本質に基づいたネタ切れ解消法はたったの2つ。
- SNS上で何かに悩んでいる・困っている発信をしている人のために記事を書く。
- 自分の身近な人が疑問に思っていることに応える記事を書く。
- ブログ運営にはペルソナの設定が重要。
- 実在する人を分析してペルソナに設定してみよう。
ブログを継続していくには、記事ごとにどのようなテーマやネタで書き上げるか悩みが出てきたり、自分が思っていたよりも早くネタ切れしてしまうものです。
だけど、「この人(のためだけ)に記事を書いてあげよう」くらいの方が、ネタも切れずに記事の構成を考えるのも簡単だったりします。
そんな時は「自分の記事が1000人に1人くらいはためになってくれれば良いな」くらい狭い内容でも良いのです。「1000人に1人」ということは、日本の人口1億人と考えて1万人のためになっているのと変わらないですからね。
人の悩みは千差万別。今日も誰か1人のためになる記事を書き続けていきましょう!
※参考にした書籍はこちら↓
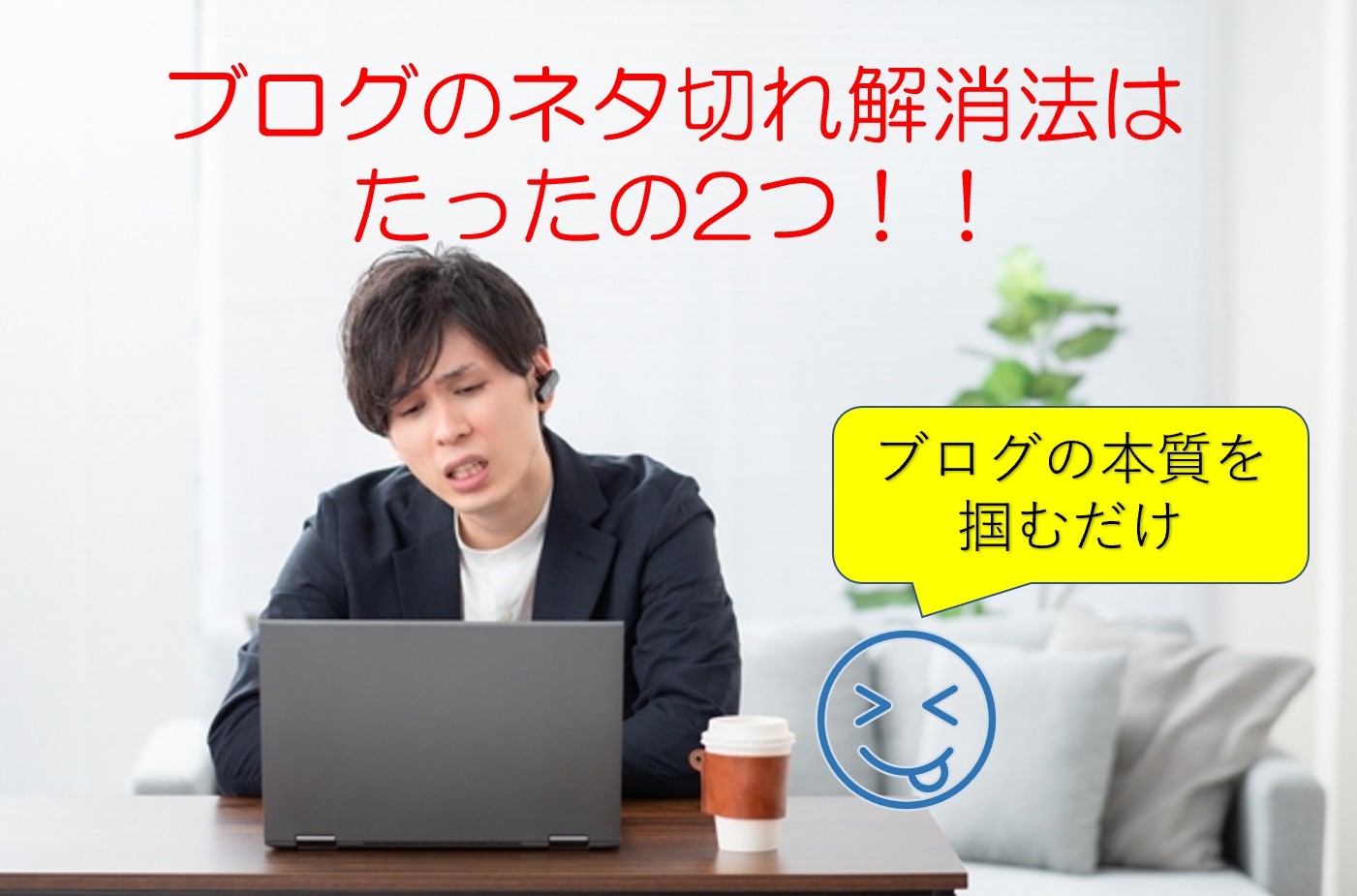


コメント