新年度がスタートして、新社会人の方も少しずつ研修を重ねながら、通常業務を覚えていく段階に入ってくるでしょう。
しかし、業務を行っていく上では、あらゆる年代の先輩と接する必要が出てきます。学校では基本的に同学年や同世代との横の繫がりばかりでしたが、仕事や社会では別の世代との関りを持つことが必須となってきます。
特に、昨今はコロナ禍ということもあり、他年代とのコミュニケーションに苦慮する若い方も多いと思いでしょう。
僕自身は現在社会人10年目ですが、若手時分は中々先輩や周囲との関係性を上手く築けず、働きにくかった経験があります。
そこで、本記事では、新社会人が先輩と上手く人間関係を構築するための指南をしていきます。この記事を読んでいる貴方が、職場の先輩たちと円滑な人間関係が出来る手助けになればと思います。
先輩と上手く人間関係を構築する方法3選
まず結論から。上手い人間関係を構築する方法は以下の3つです。
- それぞれの先輩の得意分野は何か観察する。
- パーソナルな共通項がないか確かめてみる。
- ゴルフが趣味の人はそれをアピールしてみる。または、「ゴルフやってみたいんですよね」と言ってみる。
それぞれ自身の経験も踏まえて解説していきます。
それぞれの先輩の得意分野は何か観察する。

先輩と円滑なコミュニケーションや人間関係を築くためには、まずは先輩の得意分野を観察しましょう。
誰でもそうだと思いますが、自分の好きなことや得意なことを人に話す時って、結構嬉々として話すようになるし、「自分の得意(好き)なことを聞いてくれる」と思って親しみを感じることが多いですよね。
そうは言っても、そんなにすぐ他人のことなんて分からないよ。
いちいち先輩の得意・好きなことをリサーチして話を合わせなきゃいけないの?面倒くさ。ダル…。
という声もあるでしょう。まぁもっともな意見だと思います。
このテーマでは、「見極める」ことや「調べる」ことなど、完璧を求める必要はありません。あくまでも「観察する」だけで良いのです。
観察することで生じるメリットは以下の通りです。
- 仕事そのものの流れを理解できるようになる(仕事を学ぼうとする姿勢を評価されやすい)。
- 業務で困った時に、どの先輩にどの分野のことを聞いたら分かりやすく教えてくれるか判断できるようになる(自分が1から学ぶ必要がなくなる)。
例えば、僕自身は理学療法士なのですが、理学療法士の業務はリハビリテーションの支援です。
しかし、【リハビリテーションの支援】と一言で言っても、あらゆる要素が複雑に組み合わさる奥深い仕事内容ですし、それ以外の雑多な事務作業も当たり前のようにあります。
専門職的な働きをして、それに加えて事務作業もこなしているので、先輩によっては以下のように得意な分野や知識が様々なんですね。
- A先輩:心臓リハビリの知識が豊富で、心臓リハビリチームのリーダー
- B先輩:患者さんとの関係性の作り方が上手く、クレームを言われているところを見たことが無い
- C先輩:職場のITフォーマット(ExcelシートやFileMakerプログラムなど)を分かりやすく、使いやすく作成してくれる
- D先輩:失語症(脳の病気などで上手く会話が出来ない)の知識が豊富
- E先輩:看護課の職員との仲良しが多い
- F先輩:ハンドリング(徒手療法)の技術や知識が豊富
- G先輩:装具の知識が豊富
リハビリテーションの業務をしていく中で、未熟なので分からないことも多く、「何が分からないか分からない」という最悪のパターンに陥る場合もあります。
そのような時に、どの先輩がどの分野に強みを持っているかがなんとなくでも分かっていると、
心臓のことはA先輩に聞いておけば間違いなさそうだな。
この患者さん失語かぁ…。上手いコミュニケーションの取り方を知ってそうなのはD先輩だな。聞いてみるか。
というように、自分で1から学ぶ必要もなく、得意な人のノウハウを取り入れることが出来ます。
「学ぶ」とは「まねぶ(真似る)」ことから始めよう。とも言われることがありますから、まずは、得意な人から学んで真似ることが手っ取り早いですね。
また、観察の結果、自分の見立てと先輩の得意が違うこともしばしばあります。そういう場合は他の先輩を頼れば良いのです。
パーソナルな共通項がないか確かめてみる。
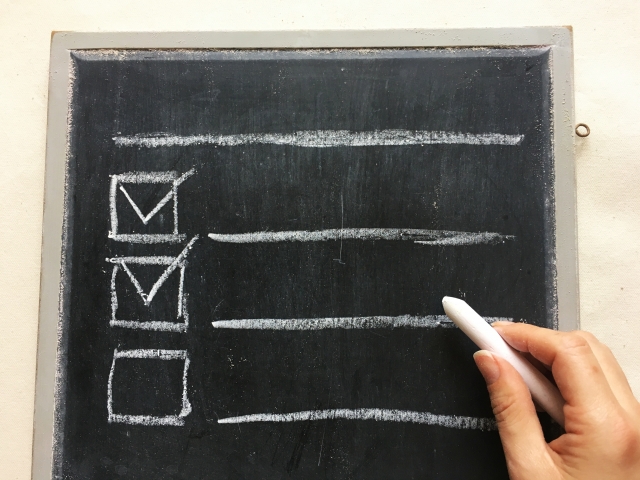
他者と人間関係を築く手法としてはありきたりですが、ありきたりだからこそ効率的だったりします。特に先輩の中でも若い世代に対しては、その先輩自身も社会人経験が少ないので、こういったありきたりな手法の方がお互いに近づきやすかったりします。
確かめてみる内容は例えば以下の項目です。
- 出身県・地域
- 出身校(高校や大学、専門学校)
- 通勤に利用している路線や国道(住んでいる地域は取り敢えずNG)
この項目のコツは、人によって熱量に差が生じるような趣味の話は後回しで良いということです。
趣味は人によって熱量に差が生じやすいため、後輩<先輩だった場合、後輩は興味も薄い先輩の濃い話を聞かされてうんざりしていまい、自分のストレスになりやすいです。
逆に、後輩>先輩だった場合、先輩にとっては立場が逆転した感覚を持ちやすいのであまり良い印象を持たれません。関係性が乏しい間は、あまり趣味の話までしなくても良いでしょう。
対して、先に挙げた3つの項目はプライベートというよりもパーソナルな部分なので、熱量に差が生じる話題にあまりなりません。
出身県や地域、出身校の共通項が見つかると、案外話題は広がったりします。
- あのお店が今でもあるか
- あの先生の授業がこんなだった
- 部活動は何をしていたか
- お互いの地域あるある
また、通勤に利用している路線や国道に関しては、「○○駅・国道●●線沿いのあのお店美味しいよ」などの話題などにも繋がりやすいですね。
人間、どんな些細なことでも他者との分かりやすい共通項があると親しみやすくなります。
また、職場で小さなトラブルやちょっとした悩み事などは、年の離れた上司よりも、年や世代の近い先輩の方が何かと頼りやすかったりします。
そのような先輩と親しくなっておくのは、自分にとっての職場環境を良い場所に出来ますから、取り入れてみてはどうでしょうか?
ゴルフが趣味の人はそれをアピールしてみる。または、「ゴルフやってみたいんですよね」と言ってみる 。

先ほど、「趣味の話はお勧めしない」と書きましたが、ゴルフに関しては、それを趣味にしている方、もしくはこれからゴルフを趣味にしたい方は、それを前面にアピールしてみることを強くお勧めします。
これは少し偏見も入りますが、大抵の職場は職場内のゴルファー人口を増やしたいと思っています。
何故かというと、ゴルフはその競技の性質上、1人では楽しめない場合が多いんですよね。
ある程度上手な人や、コミュニケーション能力の高い人、フットワークの軽い人であれば、「1人予約」で、当日になったら見ず知らずの人間同士でラウンドするということが出来るのですが、正直、精神的なハードルは高いと言わざるを得ません。
実際に、日本のゴルフ人口は徐々に減ってきていると言われ、年代が若くなるほど少ないとされています。
※参考:HALF TIME MEDIA|日本と世界のゴルフ競技人口数より
だから、ゴルフをしている・ゴルフをしたいという社員が多いほど、自身が行きたいときに誰かしら一緒にゴルフを楽しめることが出来るので、社会人ゴルファーは職場内で比較的大事に扱ってもらえます(笑)
僕自身も、実際に「ゴルフをしたい」「ゴルフやってる」というだけで、他部署との人間関係を築くきっかけになり、連携業務がスムーズにこなせるようになりました。
また、ゴルフのプレー中においても、一定のマナーを守ることが出来れば、一つ一つのプレーに対してポジティブな声掛けをしてもらえることが多いです。
普段は厳しそうに見える先輩や上司でも、ゴルフにおいてはちょっとしたミスも「大丈夫大丈夫!!」と楽しく盛り上げてくれますから、後輩の立場からしても見る目が変わるかもしれませんよ?
これからゴルフを始めようと思った人に向けて
この項を読んで「ゴルフ始めてみようかな?」と思った方には、ゴルフ5の公式オンラインショップがおススメです。
ゴルフ5のオンラインサイトからなら、ゴルフバッグや最低限必要なクラブまで揃って、およそ5万円弱で購入が可能です。
ボールの購入については、ゴルフ5のオンラインサイトよりもAmazonや楽天などの通販サイトでの購入がおススメです。
黄色は膨張色なので、飛ばした後も見つかりやすいですから、初心者でも安心です。
ティーなどの小物は先輩が持っているものを譲ってくれる場合があるので、最初のラウンドは分からなかったふりをしていると良いと思いますよ(笑)
人間関係・職場環境がキツイと思ったらすぐにでも転職や副業の検討を
これまでは社会通念上、「少なくとも3年は職場にいるべき。そのくらい働かないとその職場の良し悪しが分からない」と言われていましたが、ストレス社会の現代はそんなことを気にする必要はありません。
何故なら、その3年間で精神的に追い込まれ、働けなくなる健康状態になってしまっては元も子もないからです。
職場環境において人間関係はとても重要です。他の社員と合わないかどうかはともかく、自身の健康状態を脅かす事象(過剰なサービス残業やハラスメント)がないかどうかはすぐにでも判断した方が良いです。
転職を検討する方はこちらから↓

転職エージェントの利用はこちらから↓

副業でブログを頑張りたい方はこちらから↓
多数のブログ運営者が利用しているレンタルサーバーで、安心して利用できます(当ブログもConohaWINGを利用しています)。

まとめ
如何だったでしょうか?職場の先輩との関係性を上手に築くコツのまとめは以下の通りです。
- それぞれの先輩の得意分野は何か観察する。
- 人は自分の得意なこと、好きなことの話をすると親しく感じる。
- 得意な人を選んで教えてもらい、それを真似ることで自分のスキルアップに繋がる。
- パーソナルな共通項がないか確かめてみる。
- 出身県や出身校、利用している通勤路線や国道など。
- 共通項があるとお互いにコミュニケーションを取りやすい。
- 比較的若い先輩に有効。
- 小さいトラブルの時に頼りになるのは年の近い先輩。
- ゴルフが趣味の人はそれをアピールしてみる。または、「ゴルフやってみたいんですよね」とアピールしてみる。
- ゴルフ人口を増やしたい・維持したいので、ゴルファー社員には優しく接してくれる。
- 他部署の社員との関係性も築きやすい。
- 実際のゴルフ場面ではポジティブな言葉をかけてくれることが多い。
社会人にとって、職場環境の良し悪しを決める要素として【人間関係】は皆さんが思っているよりも大きいです。
もちろん、その職場が元々持っている空気感などにも影響しますが、職場の人間関係、少なくとも自分に関わる人間関係は、自身の行動次第でいくらでも良く出来る可能性があります。
この記事を読んだ方が、明日から職場での良い人間関係を築けるようになっていくことを願っています。
こちらのブログでは、週1回のペースで資産運用のドキュメンタリーを運営しています!ドキュメンタリー記事では、その時期の経済トピックスなどを取り上げて、資産運用初心者の方の学びになることを発信しています。
sideFIREを目指して頑張っていますので、同志の方々は一緒に学びながら頑張りましょう!!



コメント